九州の佐賀県に「吉野ヶ里遺跡(よしのがりいせき)」という、弥生時代の大規模な集落のあとが発見された場所があります。
50ヘクタールのこの広大な敷地は、現在は国営公園として整備されています。
当時の人々が住んでいた縦穴式住居や高床式倉庫、土器のお墓や防御施設などが復元されていて、誰でも中を見学することができます。
遺跡のあるこの公園の中を歩くだけで、弥生時代に人々がどんな暮らしをしていたのかよくわかる施設になっています。
この記事では、吉野ヶ里歴史公園に出かけてきたときの様子を紹介しています。
吉野ヶ里歴史公園について
弥生時代の環濠集落の跡
吉野ヶ里遺跡は、佐賀県にある日本を代表する弥生時代の環濠集落の遺跡です。
環濠集落(かんごうしゅうらく)とは、村の周りをお堀や柵などで囲んでいる集落のことです。弥生時代から稲作がはじまり、人々が米を貯蔵しはじめました。そのことから、近隣に住む人たちから食料を守る必要がでてきたのです。
この吉野ヶ里遺跡は、国の特別史跡に指定されていて、現在も復元作業が進められています。
吉野ヶ里歴史公園の見どころ
環濠入口
まず公園の東口から入場して橋を渡ると、環濠入口広場が見えてきます。
(※吉野ヶ里歴史公園には、北口、西口、東口の3つの入口がありますが、遺跡全体を見学するには、この東口から入場するのが便利です。)
環濠入口広場の辺りには、逆茂木といって、先を尖らせた木を柵のようにして、敵の侵入を防ぐ役割をする木が並んでいます。
南内郭

お堀沿いにあるき、南内郭の門の中に入りました。南内郭にはお堀や柵、物見櫓や当時の竪穴式住居が復元されています。私達が訪問した時は物見やぐらが一般解放されていて、ハシゴを使って上に登ることができました。
また縦穴式住居は内部が見学でき、王たちの部屋などを見ることができます。
弥生時代にはもう絹や麻で服が織られていて、にほんあかねという植物から、綺麗な赤い染料がつくられて糸が染められていました。またアクセサリーは勾玉と管玉、ガラスを使ったシンプルかつ精巧に作られていました。
北内郭(きたないかく)

南内郭の右手奥には、北内郭があります。北内郭には、当時祭りごとが行われていた祭殿が復元されていて、実際に登ってみることもできます。
祭殿の中では、卑弥呼を模したような姿をした女性の人が祭りごとをしています。
北墳丘墓(きたふんきゅうぼ)

北内郭の奥に進んでいくと、甕がずらりとならんだ墓の列があり、その奥には北墳丘墓があります。
北墳丘墓は、歴代の王が埋葬された墓です。
この辺りからは三千を超える壺型の土器のお墓である(甕棺)が出土されてて、埋葬された人と一緒に副葬品がおさめられていました。
一見わかりづらい場所にありますが、中を覗いてみると、立派な展示施設が建てられていました。
北墳丘墓中を見学したあと、無料の園内バスで、環濠入口広場まで戻ってきました。
吉野ヶ里歴史公園のその他の施設
これまでまわってきたルートは、ひみかのみちという、東口から北墳丘墓までの2.3キロコースで、園内で一番短い見学ルートのひとつです。
園内ではこれ以外にも村や、市場、祭壇、水田、池などがあり、グラウンドゴルフや、子供が遊ぶ遊具施設、バーベキューコーナーなども用意されていて、公園内は一周するだけでも、半日かかります。
吉野ヶ里歴史公園の見どころまとめ
弥生時代のことを学べる歴史公園
日本各地には、弥生時代の遺跡が数多くありますが、これだけの規模と数の遺跡を一度に見られる場所は、とても珍しいです。
弥生時代の人々の暮らしがどのようなものだったのか、歴史が学べる、吉野ヶ里歴史公園にぜひ出かけられてみられてはいかがでしょうか?
吉野ヶ里歴史公園のアクセス・駐車場
| アクセス | JR吉野ケ里公園駅から徒歩15分。 長崎自動車道「東脊振インター」から車で5分 |
|---|---|
| 住所 | |
| 入場料 | 大人460円(15歳未満無料) |
| 駐車場 | 有料の駐車場があります(普通車310円)。 |
周辺のホテル・旅館
周辺の観光スポット
九州地方にあるその他の観光スポットについては、こちらの記事もお読みください。
全国各地にある国営公園については、こちらの記事をお読みください。




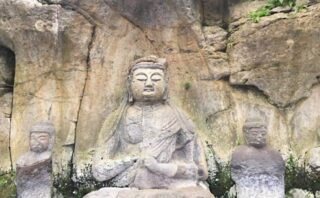
コメント